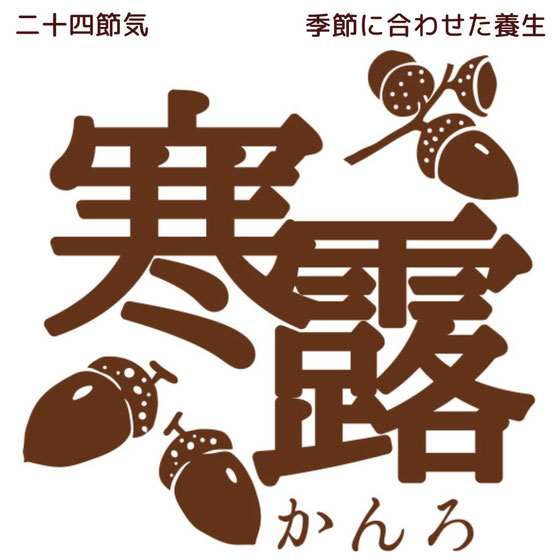養生法のこと
養生法のこと · 2024/10/19
明日10月20日から11月6日までは、「秋の土用」です。 土用とは季節の変わり目で、立春、立夏、立秋、立冬の前、それぞれ18日間程度の期間のことです。 変わり目というのは、変化への対応が必要となり、 何かと不調や不具合も起こりやすいものです。 この時期は無理をせず、穏やかに過ごすようにしましょう。 変化は「胃腸」に影響を与えます。...
養生法のこと · 2024/10/08
日中はまだまだ暑いですが、朝晩はだいぶ冷えるようになってきましたね。 今日は、二十四節気の一つ「寒露」(かんろ)です。 ※二十四節気とは、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたもの、つまり1年を24等分したものになります。 二十四節気を知っておくとより繊細に季節の移り変わりを感じることができます。...
養生法のこと · 2024/09/24
この連休は千葉に講演に行っておりまして 投稿が遅れてしまいましたが、 9月22日は、二十四節気のうちの一つ、「秋分」で、お彼岸の中日でした。 この日、真東から昇った太陽は真西に沈み、昼と夜の時間がほぼ等しくなります。 北半球ではこの日を境に、次第に昼が短く、夜が長くなります。 この日をはさんだ前後7日間が「秋の彼岸」です。...
養生法のこと · 2024/09/10
配信が遅くなってしまいましたが、 9月7日は、二十四節気のうちの一つ、「白露」(はくろ)でした。 ※二十四節気とは、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたもの、つまり1年を24等分したものになります。 二十四節気を知っておくとより繊細に季節の移り変わりを感じることができます。...
養生法のこと · 2024/08/21
明日8月22日は二十四節気のうちの一つ、「処暑」(しょしょ)です。 「処」は来て止まるという意味で、ようやく暑さが止まるという意味です。 暦の上では、暑さも収まり吹く風にも涼しさが加わる頃とされています。 ※二十四節気とは、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けたもの、つまり1年を24等分したものになります。...
養生法のこと · 2024/08/06
明日8月7日は、二十四節気のうちの一つ、「立秋」です。 暦の上では、明日から立冬の前日までが秋です。 厳しい暑さがまだまだ続いていますが、夕方の涼やかな風に秋の気配も感じられるようになってくるころで、「秋立つ」ともいいます。 立秋以降の暑さを残暑といいます。 この日以降に出す手紙の時候の挨拶は「残暑見舞い」です。...
養生法のこと · 2024/07/22
今日7月22日は、二十四節気のうちの一つ、「大暑」(たいしょ)です。 一年中で最も暑い日という意味です。 大暑から次の二十四節気である立秋(8/7)までの間が、夏の絶頂期となります。 今日はまさに「大暑」・・・ とんでもなく暑いですね・・・! 暑い時期は、汗を出すために、体中の血液が体の表面に移動します。...
養生法のこと · 2024/07/19
今日7/19から8/6までは、「夏の土用」です。 土用といえば、夏の土用の丑の日が有名ですが、 実は土用はそれぞれの季節にあります。 土用というのは季節の変わり目で、 立春、立夏、立秋、立冬の前、それぞれ18日間程度の期間のことです。 変わり目というのは、気温差が大きかったり、気候も変わりやすく不安定だったり、...
養生法のこと · 2024/07/05
明日7月6日は、二十四節気のうちの一つ、「小暑」(しょうしょ)です。 この日から暑気に入り、本格的な暑さが始まるとされます。 徐々に梅雨も明け始めます。 暑中となり、暑中見舞いも出されるようになります。 今年の場合は梅雨明けはもうちょっと先になるかもしれませんが、 梅雨明け直後はまだ身体が暑さに慣れていない為、...
養生法のこと · 2024/06/21
今日6月21日は、二十四節気のうちの一つ、「夏至」(げし)です。 一年のうちで最も昼が長い日で、この日を境に次第に日脚が短くなっていきます。 陽気の最盛期を迎える一方で、陰気がすでに芽生え始めます。 「夏に至る」と書くように、この夏至からが本格的な夏の到来です。 気温がますます上昇するとともに、雨も多いので、...
お問い合わせ・ご予約
YouTube 漢方健康みっチャンネル
チャンネル登録者、2万9千人突破!!
有野台薬品の漢方薬剤師・井上満弘が漢方や健康について分かりやすく動画で解説しています!
↓↓↓
有野台薬品スタッフのブログ
健康情報、店のこと、スタッフのことなどブログにも書いています。
のぞいてみてくださいね↓
X(Twitter)
- Twitterのメッセージを読み込み中